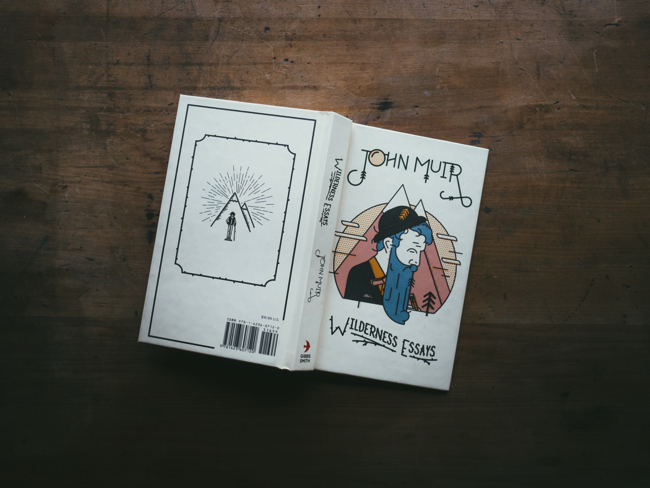
とあるパートナー企業さんの制作中のお話です。
パートナー企業さんは、その分野での専門家です。そんな方から、エンドユーザー様向けの制作物を頼まれました。
〇〇をもっと知ってもらいたいから、△△な内容を入れて欲しい。
というご要望でしたが、お客様のことを考えると、どうしても△△という内容を入れることができなく、抽象的な言葉での表現を選んでご提案させていただくこともあります。
エンドユーザー様向けの制作物をつくる際に、このような現場でのやりとりはよく起こります。
このような場合の話し合いで大事なことは「どちらの意見が正しいか?正しくないか?」という結論ではなく『どちらが、御社の消費者さん向けの表現か?』という判断軸が大事になります。
専門家すぎる経営者ほど、その軸がブレてしまうケースも多いです。
表現の仕方が、いかに戦略的か?、どれくらいユーザー目線か?、というのは、広告デザインではもっとも大事なポイントです。
なぜなら、その表現が売り上げに直結するからです。
Contents
売上げにつながるお客様の知識はどれくらい?
御社の消費者を選ぶ時に重要なことは、売上げにつながる知識量の人を見つけること。
例えば、眼科がレーシックのパンフレットをつくる場合は、当社で利用してくれるだろう患者様(見込み客)が、視力をどのように克服しようとしているか?が勝負所(論点)になることは間違いありません。
そうなると最初に気になるのは、視力を克服したいと考えているお客様のこと。
視力を克服する場合に対象(競合)となるのは、[メガネ、コンタクト、レーシック、マッサージ、睡眠、目薬]など、多くの手段があります。
そんな中でも、御社のレーシックを受けてもらわなくてはいけませんから、レーシックの素晴らしさを伝えていかなくてはなりません。

なぜなら、メガネよりも素晴らしく、コンタクトよりも素晴らしいレーシックであることを伝えなくては、お客様にはレーシックを選んでいただくことができないからです。
では、どんなことを掲載すると良いのか?を、少しだけ具体的にしてみたいと思います。
よくありがちな『説明書のようなパンフレット』の製作
専門家だからこそありがちなのは、レーシックについての専門書のような内容を伝えてしまうことです。実はこれでは大失敗(無駄な投資になる)します。
なぜならエンドユーザーは、専門知識を知りたいのではなく、どんなレーシックが自分に合っているか?を知りたいからです。
パンフレットの場合は特に、当眼科のレーシックは、あなたの生活(状態)をどれほど素晴らしいものにするか?が書かれていなくてはなりません。
もしレーシックをやろうと決めている人なら、どの眼科のレーシックが自分にあっていそうか?を探しているはずです。
でも、そんな患者さまに向けて、まるで学校の先生かのように専門知識をお披露目しても、お客様に興味が湧くはずはありません。
もし、レーシックに興味がない患者さまが専門書のような内容を読んでいたら、きっと眠くなってしまうでしょう。
専門知識を知りたい人は、
専門知識が書いてあるパンフレットをもらっても、そのサービスを受けない
ここがユーザー心理の中で、最も判断基準が難しいポイントではないかと思います。
つまり、どれほどの興味がある患者さんに、どのような内容をお伝えするか? が重要な判断ポイントになるのです。
その際、すでに分かっていることがあると言えば、
- どんなレーシックが自分に合っているか?を知りたい人は『検索』をして自分で探している
- レーシックに興味がない人(長年、メガネ派、コンタクト派)はレーシックを選びにくい
という事実です。

自分に合ったレーシックを探している人は、様々な眼科を『検索』して比較検討をしていますから、わざわざ当院のパンフレットを読むことはありません。
また、長年メガネをかけている人やコンタクト生活をしている人は、よほどの衝撃的なことが起きない限りレーシックを選ばないでしょう。
そう考えると、おのずと複数人の対象となる患者さんの姿が思い浮かびます。
- 最近、突然目が悪くなった人
- 視力が衰えてきたことに恐怖を感じている人
- 目が悪いことは理解しているけど、そのまま生活を続けてしまっている人
- 視力が悪すぎてメガネの厚みが気になる人
- コンタクトレンズを使うことに抵抗を感じている人
これらの患者さんに、いくら専門用語を使った詳しいパンフレットを渡しても、理解してもらえるはずがないことはわかると思います。
このように、アプローチするお客様を決めることは、掲載内容や見た目を決めることよりも重要なのです。
患者さんが、眼科のパンフレットに求めていること
では一体、お客様にとって、パンフレットにはどのような内容が書かれていると良いのでしょう?
それは『当眼科では、〇〇なお客様のために、△△なレーシックプランを用意しています』という内容です。
つまり『自分の理想の施術か?』『自分の将来にとって最適な施術か?』を判断しています。
その上で『価格が自分の財産(使えるお金)に見合いっているか?』を判断しています。
経営者あるあるでは「金額が高いからお客様に利用していただけないんだ。」とお考えの方がいらっしゃいますが、それは全く違います。
お金と時間を投資する価値を感じない商品(サービス)を届けている。が正解です。
そのことからも、どのような人に、どんな案内を提示するか。を決めることは、ある意味では、見栄えよりも大事なことだと認識しておくことが重要だといえるでしょう。
コミュニケーションをゴールにする
すべてのツールは、お客様との関係性、社員との関係性を深めるためのものです。
ですから、案内を読んで安心してもらうことができれば、そのパンフレットを読んだ後に、先生や看護師さんに聞いてくれることをゴールにしてもらえなくては、作る意味はありません。
- 痛みは?
- どれほどの期間、目が見えないのか?
- 術後の経過(フォロー)について
- 詳しい金額について
これらを直接聞いてもらうことができれば、あとは患者さんの要望を伺うだけです。
ですが、その行動(患者さんとの無駄話の時間)が効率的ではないと考えてしまったり、競合企業よりもうちは優れていることを証明したい!と考えてしまったり、制作費の損得の気持ちが強くなってしまうと
少しでも得をしたい!という気持ちから、あれもこれも詰め込みたくなるのでしょう。
ですが、社員やお客様とのコミュニケーションの場をつくるため。という目的を元に、広告媒体の制作を行ってもらえれば、より良いデザイン制作が行えます。
お客様とのコミュニケーションの場が利益を生みます。人と人との関係性の向上を目指すデザイン製作に励んでもらいたいと思います。
外部から見る強みは、客観的であること
外部デザイナーが、インハウスデザイナーより優っている点は、客観的な判断軸を持っているという点です。
ほとんどのお客様は、先生や専門職の人ほど知識を持っていません。
だからこそ、どれほどの知識を持ったお客様にどんな案内するのか?ということを話し合えなくては、広告戦略もデザイン戦略も上手くいかないといえるでしょう。
デザイナーの技術で大事なのは、見た目のデザイン制作の技術よりも、客観性とユーザー心理への関心です。
すべての中小企業が、より良いデザイナーと手を組み、より良い成果を伸ばしてもらいたいと願っています。
サブファイでは、御社のプロデュースにつながるデザイン媒体の制作を企画提案させていただいております。
そのため、戦略や企画にも参画させていただき、社員教育としてセミナーを行わせていただきながらデザインディレクションを行っています。
経営者様を含め、社員の方々(当人たち)のやる気次第、計画次第では、劇的な変化につながります。
ご相談から伺っています。ぜひ、お気軽にご相談ください。



Average Rating